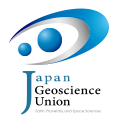| 2011年08月10日 | 10月9日 東日本大震災シンポジウム―地球人間圏学の視点 ―東日本大震災の教訓を生かして 南 海・東南海地震に備えるために― |
東日本大震災シンポジウム―地球人間圏学の視点
―東日本大震災の教訓を生かして 南 海・東南海地震に備えるために―
日 時: 2011年10月9日(日) 13:00から18:15
場 所: 関西大学(百周年記念会館ホール)
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35、
阪急電鉄「梅田」駅から千里線「北千里」行で「関大前」駅下車(この間約20分)、徒歩約5分。
または京都「河原町」行(通勤特急を除く)で「淡路」駅下車、「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。
参 加 費: 無料 事前申し込み不要
プログラム:
東日本大震災シンポジウム―地球人間圏学の視点 ―東日本大震災の教訓を生かして 南 海・東南海地震に備えるために―
総合司会:春山成子 (日本学術会議連携会員 三重大学教授)
13:00 挨拶 関西大学副学長
13:05 シンポジウム開会の挨拶
岡部篤行
(日本地球惑星科学連合 地球人間圏セクション プレジデント
青山学院大学教授)
第1部 東北地方太平洋沖地震と津波、被害の実態を科学的に知る
13:10 「超巨大海溝型地震・津波対策の再考」
河田 恵昭 (日本学術会議連携会員 関西大学教授)
13:40 「東北地方太平洋沖地震に学ぶ超巨大海溝型地震の特徴と今後の地震対策 」
入倉孝次郎 (日本学術会議連携会員 京都大学名誉教授)
14:10 「堆積物からみた日本海溝における海溝型巨大地震の履歴」
澤井 祐紀 (独立法人産業技術総合研究所 主任研究員)
14:40 「巨大南海地震の繰り返し間隔と規模」
岡村 真 (高知大学教授)
15:10 「長期的地震危険度評価の方法・成果と課題」
奥村 晃史 (日本学術会議連携会員 広島大学教授)
15:40 「仙台・石巻平野における津波の流動」
海津 正倫 (日本学術会議特任連携会員 奈良大学教授)
休憩 16:10-16:20
第二部 災害を次世代に引き継ぐために―自然と人間とのかかわりを考える―
16:20 「地域レベルでの防災対応や防災教育は、津波減災にどう役立ったか」
宮城 豊彦 (東北学院大学教授)
16:40 「東日本大震災を生徒に教えるための指針策定と教材作成
―「温度差」 のある関西の教育現場からの提言―」
野間 晴雄 (日本学術会議連携会員 関西大学教授)
下村 勝哉 (兵庫県立津名高校教諭)
小泉 邦彦 (西宮市立上甲子園中学校教諭)
17:00 「地理基礎・歴史基礎必修化の提言と地図/GISを活用した防災教育の推進」
碓井 照子 (日本学術会議会員 奈良大学教授)
第三部 パネルディスカッション 17:30~18:10
東日本大震災の教訓を活かすために ―南海・東南海地震に備えて―
18:10 閉会の挨拶 氷見山幸夫 (日本学術会議連携会員 北海道教育大学教授)
18:15 終了
その他のお知らせ
| 2025.07.03 | ホームページサーバーメンテナンスのお知らせ |
|---|---|
| 2025.06.17 | 訂正とお詫び(メールニュース 6月号 No.405(2025/06/13)) |