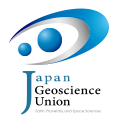イベント情報
現在21件の情報が登録されています。
2026-03-18
2026-02-20 16:59:30
情報登録日:2026年02月20日 (No.451)
学術シンポジウム
応用統計学フロンティアセミナー
開催日
2026年03月18日
会場
オンライン開催オンライン
主催
応用統計学会
詳細
AI が拓く⾃然科学の新時代 〜AI が解き明かす物理・地球・宇宙の真理〜
現在の第三次AIブームはとどまるところを知らず、自然科学においても、いずれAIが人類に代わって新発見をもたらす時代がやって来ることを予感させています。しかしながら、常に「なぜ」を問い続けることによって真理を究明してきた自然科学においては、現在のAIはまだ十分なツールとはなっていません。
本セミナーでは、最先端の情報科学や統計学を駆使した物理学・地球科学・天文学のご研究をされているトップリーダーを講師としてお招きし、各分野における現在のAI研究の現状を踏まえてAIが拓く自然科学の将来像についてご講演頂きます。
現在の第三次AIブームはとどまるところを知らず、自然科学においても、いずれAIが人類に代わって新発見をもたらす時代がやって来ることを予感させています。しかしながら、常に「なぜ」を問い続けることによって真理を究明してきた自然科学においては、現在のAIはまだ十分なツールとはなっていません。
本セミナーでは、最先端の情報科学や統計学を駆使した物理学・地球科学・天文学のご研究をされているトップリーダーを講師としてお招きし、各分野における現在のAI研究の現状を踏まえてAIが拓く自然科学の将来像についてご講演頂きます。
2026-03-10
2026-02-17 11:41:06
情報登録日:2026年02月17日 (No.450)
学術シンポジウム
海と地球のシンポジウム
開催日
2026年03月10日~03月11日
会場
東京都東京大学弥生キャンパス
主催
東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構
詳細
「海と地球のシンポジウム2025」
・開催期間:2026年3月10日(火)~2026年3月11日(水)
・会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール
・オンライン開催あり
・参加費:無料(事前登録制)
・参加登録締切:2026年2月20日(金)
〇参加登録:以下URLよりお願いいたします。
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/entry.html
〇懇親会参加登録:以下URLよりお願いいたします。
https://forms.gle/7cbEdffgy5x9cZ6cA
・開催期間:2026年3月10日(火)~2026年3月11日(水)
・会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール
・オンライン開催あり
・参加費:無料(事前登録制)
・参加登録締切:2026年2月20日(金)
〇参加登録:以下URLよりお願いいたします。
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/entry.html
〇懇親会参加登録:以下URLよりお願いいたします。
https://forms.gle/7cbEdffgy5x9cZ6cA
2026-03-21
2026-02-07 23:28:03
情報登録日:2026年02月07日 (No.448)
一般公開イベント
中高生向け湯之奥金山(茅小屋金山)地学実習
開催日
2026年03月21日
会場
山梨県山梨県身延町湯之奥金山
主催
日本地球科学普及教育協会
詳細
本実習は、高校理科の中でも履修者の少ない地学について、中高生向けに実際の野外実習を提供することで、参加者が基礎知識を獲得し、将来的に社会へ応用できる環境を育むことを目的に実施しています。
湯之奥金山は、山梨県身延町にある中山金山、内山金山、茅小屋金山とあわせた総称で、戦国時代から江戸時代半ばにかけて稼働していた金山遺跡です。地質学的には南部フォッサマグナと呼ばれ、日本列島の東北側と西南側の地質学的境界にあたります。この実習では、地形図を見ながらプレートテクトニクスの観点で湯之奥金山の位置付けを知り、金山遺跡を見ながら、金山から流れる沢の岩石を観察し、金山を生み出した地質変動の痕跡を探ります。
湯之奥金山は、山梨県身延町にある中山金山、内山金山、茅小屋金山とあわせた総称で、戦国時代から江戸時代半ばにかけて稼働していた金山遺跡です。地質学的には南部フォッサマグナと呼ばれ、日本列島の東北側と西南側の地質学的境界にあたります。この実習では、地形図を見ながらプレートテクトニクスの観点で湯之奥金山の位置付けを知り、金山遺跡を見ながら、金山から流れる沢の岩石を観察し、金山を生み出した地質変動の痕跡を探ります。
2026-03-14
2026-02-05 12:55:11
情報登録日:2026年02月05日 (No.447)
学術シンポジウム
第2回MLFロードマップワークショップ
開催日
2026年03月14日
会場
茨城県水戸市民会館
主催
J-PARCセンター(JAEA&KEK)
詳細
中性子・ミュオンビームを活用した科学のさらなる発展には、施設とユーザーとの密接なコミュニケーションを通じて、相互に知見を深め、高め合うことが不可欠です。本ワークショップは、MLFの将来計画についてユーザーの皆様と議論を重ね、具体化していくことを目的としており、今後2年間で計4回程度の開催を予定しています。
2025年8月26日に開催した第1回ワークショップでは、活発な意見交換が行われました。これを受けて、第2回となる今回は、施設とユーザーの双方向的な議論をさらに深め、MLF将来計画の方向性を共有する貴重な機会としたいと考えております。皆様の積極的なご参加を、心よりお待ち申し上げます。
2025年8月26日に開催した第1回ワークショップでは、活発な意見交換が行われました。これを受けて、第2回となる今回は、施設とユーザーの双方向的な議論をさらに深め、MLF将来計画の方向性を共有する貴重な機会としたいと考えております。皆様の積極的なご参加を、心よりお待ち申し上げます。
2026-08-31
2026-02-05 11:47:08
情報登録日:2026年02月05日 (No.446)
国際シンポジウム
FOSS4G Hiroshima 2026
開催日
2026年08月31日~09月05日
会場
広島県広島市
主催
FOSS4G Hiroshima 2026 現地組織委員会
詳細
地球惑星科学分野においても技術の活用が不可欠な、オープンソースの地理情報システム(GIS)に関する世界最大の国際会議です。
会期:2026年8月30日(日)〜9月5日(土)
会場:
・広島国際会議場(メイン会場)ほか
論文募集期間:
・アカデミックトラック:2026年3月2日 アブストラクト締切
・一般セッション:2026年3月16日 申込締切
・ワークショップ:2026年3月16日 申込締切
会期:2026年8月30日(日)〜9月5日(土)
会場:
・広島国際会議場(メイン会場)ほか
論文募集期間:
・アカデミックトラック:2026年3月2日 アブストラクト締切
・一般セッション:2026年3月16日 申込締切
・ワークショップ:2026年3月16日 申込締切
2026-04-20
2026-02-04 13:59:03
情報登録日:2026年02月04日 (No.445)
一般公開イベント
2026年度第1回 地質調査研修
開催日
2026年04月20日~04月24日
会場
福島県茨城県つくば市(産総研)・ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺
主催
産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」
詳細
"内容
2026-03-28
2026-02-04 08:25:04
情報登録日:2026年02月04日 (No.444)
一般公開イベント
市民向け講座・野外観察会「大地の成り立ちを探ろう」
開催日
2026年03月28日
会場
愛知県愛知教育大学および洲原公園(愛知県刈谷市)
主催
日本地学教育学会中部支部
詳細
地質学の専門家(星 博幸・愛知教育大学教授)と一緒に、身近な土地の岩石や地層を観察して、身のまわりの大地がどのように成り立ってきたかについて考えてみましょう! きっと驚きと発見がありますよ!!
2026-03-02
2026-01-28 14:04:07
情報登録日:2026年01月28日 (No.443)
学術シンポジウム
ムーンショット目標10 新規プロジェクト・キックオフシンポジウム
開催日
2026年03月02日
会場
東京都JST東京本部別館1階ホールおよびオンライン(Zoomウェビナー)
主催
国立研究開発法人科学技術振興機構
詳細
フュージョン技術は、これまでのエネルギー技術にはないさまざまな特長を活かした多様な利用法が期待されています。特に、地球上に広く分布し、海水にも豊富に含まれる「軽元素」を燃料とすることで、資源争奪の問題が緩和され、持続可能で基幹的なエネルギー源となる可能性を秘めています。いま、各国が熾烈な開発競争を繰り広げている中で、ムーンショット目標10(以下、「目標10」)では、フュージョンリアクターの実現に向けて主路線の開発にとどまらず、フュージョンエネルギーの高付加価値化(早期実現・高経済性・高信頼性・極限技術の汎用化)につながるイノベーションを生み出し、それを主路線開発へ還元することを目指しています。
2026-03-04
2026-01-22 11:11:04
情報登録日:2026年01月22日 (No.441)
一般公開イベント
石油開発 冬の学校2026 in 新潟
開催日
2026年03月04日~03月06日
会場
新潟県新潟県長岡市
主催
日本石油ガス学生団体(NOGS)
詳細
石油開発 冬の学校は、石油開発に関心を持つ学生が全国から集まる合宿型のイベントです。
例年は東京で座学中心に実施している「石油開発 夏・冬の学校」ですが、今回は出張版として新潟県長岡市で開催し、実際の石油・ガス開発現場の見学もプログラムに含まれています。教室を飛び出し、リアルな現場を体感できる特別な冬の学校です。
石油開発に関する知識を深められるだけでなく、他大学の学生や石油開発企業の方々と交流できる、非常に有意義な機会となっております。
【応募締切】
2026年1月31日(土)23時59分
例年は東京で座学中心に実施している「石油開発 夏・冬の学校」ですが、今回は出張版として新潟県長岡市で開催し、実際の石油・ガス開発現場の見学もプログラムに含まれています。教室を飛び出し、リアルな現場を体感できる特別な冬の学校です。
石油開発に関する知識を深められるだけでなく、他大学の学生や石油開発企業の方々と交流できる、非常に有意義な機会となっております。
【応募締切】
2026年1月31日(土)23時59分
2026-07-05
2026-01-14 18:54:04
情報登録日:2026年01月14日 (No.434)
国際シンポジウム
第32回国際レーザレーダ会議 (ILRC32) --発表申込・予稿提出 締切延長--
開催日
2026年07月05日~07月10日
会場
広島県広島国際会議場
主催
一般社団法人レーザセンシング学会
詳細
ILRC32の発表申込・予稿提出の締切が延長され、2026年2月5日となりました。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1)開催日程:2026年7月5日(日)〜7/10日(金)
2)会場:広島国際会議場(広島県広島市)
3)主なスケジュール:
発表申込・予稿提出締切:2026年1月5日 => 2026年2月5日
早期参加申込締切:2026年5月7日
4)会議website:https://smartconf.jp/content/ilrc32/
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1)開催日程:2026年7月5日(日)〜7/10日(金)
2)会場:広島国際会議場(広島県広島市)
3)主なスケジュール:
発表申込・予稿提出締切:2026年1月5日 => 2026年2月5日
早期参加申込締切:2026年5月7日
4)会議website:https://smartconf.jp/content/ilrc32/
2026-03-27
2026-01-09 19:42:05
情報登録日:2026年01月09日 (No.433)
一般公開イベント
「気候変動と大気汚染 ―短寿命気候強制因子の影響と緩和―」 公開ウェビナー第12回
開催日
2026年03月27日
会場
オンライン開催Zoomウェビナー および YouTubeライブ配信
主催
環境研究総合推進費S-20プロジェクト
詳細
排出源および大気中の時空間分布が偏在している短寿命気候強制因子 (SLCF)の地域ごと及び組成ごとの気候変動・環境影響を定量的に評価し,同時に影響緩和へ向けた排出量削減シナリオを策定するための研究を推進しているプロジェクトによるウェビナー.
第12回「短寿命気候強制因子(SLCFs)の排出インベントリ:アジアにおける近年の排出量とその変化」黒川純一
第12回「短寿命気候強制因子(SLCFs)の排出インベントリ:アジアにおける近年の排出量とその変化」黒川純一
2026-03-23
2026-01-06 23:04:02
情報登録日:2026年01月06日 (No.430)
一般公開イベント
理系大学生のための太陽研究最前線体験ツアー 受講生募集
開催日
2026年03月23日~03月27日
会場
東京都名古屋大学,京都大学飛騨天文台,JAXA宇宙科学研究所,国立天文台三鷹
主催
太陽研究者連絡会
詳細
太陽研究最前線体験ツアーは理系学部(教育学部含む)の大学生で、大学院での太陽に関する研究に興味のある方、最新の太陽研究に興味のある方などを対象に、 国内の主要な太陽研究機関を5日間で一度に訪問するツアーです。国際的に活躍している太陽研究者らが、太陽研究や観測施設の最前線を紹介します。
旅程や応募方法・応募条件などの詳細は以下のWebページからご参照いただけます。
https://jspc.sakura.ne.jp/sun_tour/
旅程や応募方法・応募条件などの詳細は以下のWebページからご参照いただけます。
https://jspc.sakura.ne.jp/sun_tour/
2026-07-05
2025-12-26 13:51:08
情報登録日:2025年12月26日 (No.429)
国際シンポジウム
第32回国際レーザレーダ会議 (ILRC32)
開催日
2026年07月05日~07月10日
会場
広島県広島国際会議場
主催
一般社団法人レーザセンシング学会
詳細
ILRC32はライダやレーザセンシングの技術と応用に関する国際的な学術会議です。ライダ・レーザセンシング技術と共に、それらを用いた衛星・航空機・地上等からの大気・海洋・陸域・生態系観測、宇宙探査、そして数値モデルを組み合わせた応用研究など、幅広い研究分野を対象としています。また、レーザ、光学機器などの関連企業様からの協賛(会場展示や広告掲載)も広く募っています。皆様のご参加をお待ちしています。
会場:広島国際会議場(広島県広島市)
現地対面:口頭発表、ポスター発表、企業展示
発表申込・予稿提出締切:2026年1月5日
早期参加申込締切:2026年5月7日
会場:広島国際会議場(広島県広島市)
現地対面:口頭発表、ポスター発表、企業展示
発表申込・予稿提出締切:2026年1月5日
早期参加申込締切:2026年5月7日
2026-03-03
2025-12-24 15:21:04
情報登録日:2025年12月24日 (No.427)
学術シンポジウム
STAR-Eプロジェクト 第5回研究フォーラム(研究成果公開シンポジウム)
開催日
2026年03月03日
会場
オンライン開催オンラインにて配信いたします。
主催
文部科学省
詳細
情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト(STAR-Eプロジェクト)第5回研究フォーラム 情報科学×地震学
研究成果公開シンポジウム ~知をつなぎ、地震防災技術を拓く~
概要:STAR-Eプロジェクトの最終年度を迎え、研究成果を広く公開します。
地震研究と情報科学の融合によって生まれた知見を、防災や情報発信の技術へどう活かし、どう社会に役立てるのか。その道筋をわかりやすく紹介します。
研究成果公開シンポジウム ~知をつなぎ、地震防災技術を拓く~
概要:STAR-Eプロジェクトの最終年度を迎え、研究成果を広く公開します。
地震研究と情報科学の融合によって生まれた知見を、防災や情報発信の技術へどう活かし、どう社会に役立てるのか。その道筋をわかりやすく紹介します。
2026-04-01
2025-12-20 09:18:10
情報登録日:2025年12月20日 (No.426)
学術シンポジウム
「IPY-5国内メーリングリスト」登録のご案内
開催日
2026年04月01日~2033年12月31日
会場
オンライン開催国立極地研究所
主催
IPY-5日本国内委員会
詳細
2032-33年に開催されます第5回国際極年(The Fifth InternationalPolar Year(IPY-5))に向けて日本として対応するため、「IPY-5日本国内委員会」が2026年4月に発足致します。発足に伴いまして、関心のある皆様へ定期的に国内外のIPY-5関連情報をお知らせする為、「IPY-5国内メーリングリスト」を作成する事となりました。IPY-5へご関心ある方は、登録Formよりご登録をお願い致します。既にJCAR(北極環境研究コンソーシアム)メーリングリストへご登録いただいています方には、こちらへご登録いただかなくても、自動的に同じ情報が届きます。
2026-03-11
2025-12-15 16:35:04
情報登録日:2025年12月15日 (No.422)
学術シンポジウム
2025年度量子ビームサイエンスフェスタ
開催日
2026年03月11日~03月13日
会場
茨城県水戸市民会館
主催
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所他
詳細
量⼦ビームは学術から産業にわたる広い分野において、その研究開発を⽀える重要なツールとして⽋かせない役割を担っており、KEK 放射光実験施設(PF)とJ-PARC 物質・⽣命科学実験施設(MLF)は放射光・陽電⼦と中性⼦・ミュオンのそれぞれの特徴を活かしたマルチプローブ利⽤による新しいサイエンスが広がりを⾒せています。
本フェスタは、施設スタッフとユーザーとの情報交換の場であるだけでなく、異なるプローブを⽤いる研究者間の交流を通して将来の量⼦ビーム利⽤研究のあり⽅を考える場となることを⽬指しております。
本フェスタは、施設スタッフとユーザーとの情報交換の場であるだけでなく、異なるプローブを⽤いる研究者間の交流を通して将来の量⼦ビーム利⽤研究のあり⽅を考える場となることを⽬指しております。
2026-03-10
2025-12-08 17:36:18
情報登録日:2025年12月08日 (No.420)
学術シンポジウム
「海と地球のシンポジウム2025」
開催日
2026年03月10日~03月11日
会場
東京都東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
主催
東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構
詳細
「海と地球のシンポジウム2025」
発表課題募集〆切まであと5日!:2025年12月12日(金)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/invitation.html
研究船等を利用された皆様、こちらのシンポジウムにて航海速報や研究成果などをご発表ください。
参加登録もお待ちしております!
海と地球のシンポジウム実行委員会
ocean.and.earth.symposium@jamstec.go.jp
発表課題募集〆切まであと5日!:2025年12月12日(金)
https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/invitation.html
研究船等を利用された皆様、こちらのシンポジウムにて航海速報や研究成果などをご発表ください。
参加登録もお待ちしております!
海と地球のシンポジウム実行委員会
ocean.and.earth.symposium@jamstec.go.jp
2026-03-10
2025-11-21 10:43:08
情報登録日:2025年11月21日 (No.418)
学術シンポジウム
「海と地球のシンポジウム2025」開催案内および発表課題登録&参加登録案内
開催日
2026年03月10日~03月11日
会場
東京都東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール
主催
東京大学大気海洋研究所、海洋研究開発機構
詳細
東京大学大気海洋研究所と海洋研究開発機構は、研究船等を利用して得られた成果の報告会として「海と地球のシンポジウム2025」を2026年3月10日〜11日に開催します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
・ホームページ:https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/
・開催日時:2026年3月10日(火)〜3月11日(水)
・会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
・ホームページ:https://www.jamstec.go.jp/j/pr-event/ocean-and-earth2025/
・開催日時:2026年3月10日(火)〜3月11日(水)
・会場:東京大学弥生キャンパス 弥生講堂
2026-03-10
2025-09-25 11:56:04
情報登録日:2025年09月25日 (No.402)
学術シンポジウム
「海と地球のシンポジウム2025」開催および発表課題募集のお知らせ
開催日
2026年03月10日~03月11日
会場
東京都東京大学弥生キャンパス
主催
東京大学大気海洋研究所と 海洋研究開発機構の共催
2026-03-09
2025-08-18 00:25:03
情報登録日:2025年08月18日 (No.396)
学術シンポジウム
変形・透水試験機設計セミナー2026
開催日
2026年03月09日~03月11日
会場
京都府京都大学 吉田キャンパス
主催
試験機設計セミナー世話人
詳細
“変形と物質移動”は,テクトニクス・地震・地球内部流体循環・環境問題・応用地質など多くの分野に関わる基本的なプロセスです.自然界でおこっている変形と物質移動のプロセスを動的に捉えるためには,岩石の組織や構造の解析に加えて,それらのプロセスを実験的に再現する必要があります.本セミナーでは,岩石の変形と物質移動を調べるための試験機の実用的な設計法を取り上げます.セミナーの最後には,参加者全員が標準的な変形・透水試験機の図面を作成して,発表会を行う予定です. 試験機の設計は,ポイントを押さえることができれば決して難しいものではありません.皆様(特に学生)の参加をお待ちしております.
2026-11-02
2025-08-05 16:59:04
情報登録日:2025年08月05日 (No.391)
国際シンポジウム
第10回国際窒素会議(N2026)
開催日
2026年11月02日~11月06日
会場
京都府国立京都国際会館
主催
国際窒素イニシアティブ、第10回国際窒素会議組織委員会、総合地球環境学研究所
JpGU後援
詳細
N2026は「持続可能な窒素管理を将来世代のために」を主題に掲げ、窒素問題に関する多様な分野の専門家に加え、国内外の政策関係者およびその他の多様なステークホルダーが集い、窒素問題の現状と将来に関する科学的知見の集積と共有を図り、実効性の高い窒素管理に向けた課題を議論する場として開催されます。窒素問題が関与する幅広い学問分野からの最新の研究成果および国内外の窒素管理に向けた実践経験を共有する機会となります。